自己肯定感の高め方を知りたい人へのおすすめ本10選【2025年最新版】気持ちを楽にする簡単な方法をマスターしよう

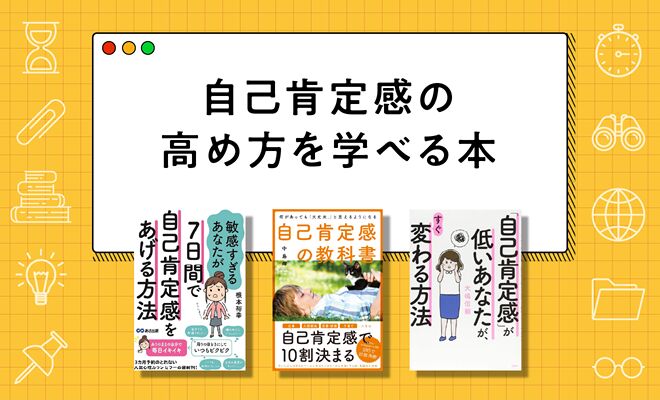
自己肯定感とは、自分をありのまま受け入れ、肯定し、認められる感覚のこと。近年、「自己肯定感が低くてつらい」「自己肯定感を高めて、自分を認めてあげたい」といった悩みをよく耳にするようになりました。書店には、自己肯定感の上げ方を解説する書籍が多く並んでいます。
そこで本記事では、自己肯定感の定義から高め方までを学べる本を10冊ピックアップしました。気になったものがあればぜひチェックしてみてください。
「自己肯定感」が低いあなたが、すぐ変わる方法
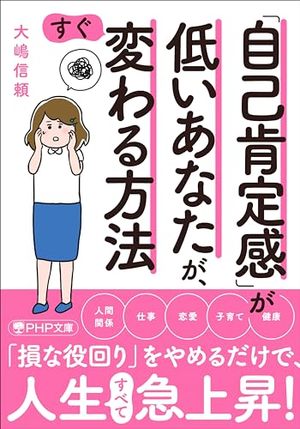
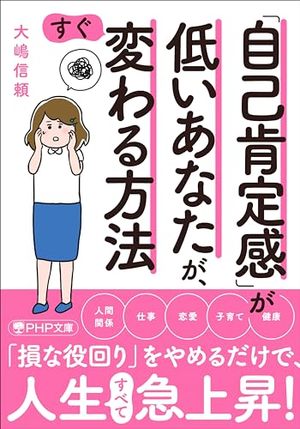
自己肯定感を高める方法を知る前に、まず「どうして自己肯定感が高いほうがいいの?」という疑問を解消したいなら、『「自己肯定感」が低いあなたが、すぐ変わる方法』がおすすめです。
本書では、心理カウンセラーの大嶋信頼さんが、自己肯定感が低い人は損な役回りをさせられていると指摘します。自己肯定感が低いほうが愛されるという幻想を持っているため、自ら失敗して、自己肯定感を下げてしまうのです。
また、自己肯定感が低いと他人と対等になれないとも指摘されています。自己肯定感が高い人は「自己肯定感が低い人とつき合ってもメリットがないから」と去っていき、自己肯定感が低い人には利用されてしまうためです。
続いて、自己肯定感の高め方を見ていきましょう。ここで紹介するのは、ほしいものを考えること。
大嶋さんによると、本当にほしいものを思い浮かべると自己肯定感が高まり、それまでできなかったこともできるようになります。あなたも「自分はダメだ」と自己肯定感が下がったら「高級マンションがほしい」などと、自分が本当にほしいものを思い浮かべてみましょう。嫌な気持ちがスッと消えるでしょう。
大嶋さんは、自己肯定感が低い人は、自分のほしいものについて考えないクセがついているといいます。なぜなら、「自分には無理だ」と思ってしまうためです。
あなたも「自分はダメだ」と思ったら、ほしいものをイメージする習慣をつけてみてください。自分の欲求に素直になることが、自己肯定感を高める第一歩なのです。
何があっても「大丈夫。」と思えるようになる自己肯定感の教科書
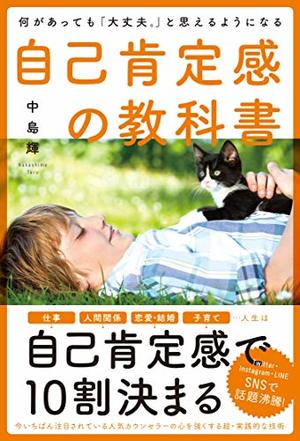
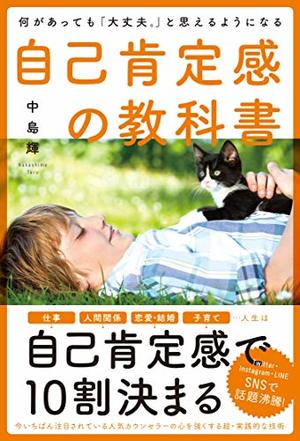
「自己肯定感の第一人者」という肩書きを持つ心理カウンセラー、中島輝さんの著書、『何があっても「大丈夫。」と思えるようになる自己肯定感の教科書』にもご注目ください。
本書では、自己肯定感は「人生を支える軸となるエネルギー」と表現されています。また、自己肯定感は周囲の環境などによって上がったり下がったりするもので、もともと自己肯定感が高い人と低い人がいるものの、何歳からでも後天的に育てられると断言されています。
本書の特徴は、自己肯定感の高め方が、瞬発型の「自己肯定感がパッと一瞬で高まる方法」と、持続型の「自己肯定感をじわじわと高める方法」という2つの方向性で紹介されていること。この2つを組み合わせて取り組み、1つのワークを達成したときに、自分に対して「よくやったね」といったご褒美の言葉をかけることで、自己肯定感が高まっていくとされています。
短期的な自己肯定感の高め方として挙げられているのは、週末こそ早起きすること。休日なら、眠くなっても好きなときに仮眠できます。まずは思い切って早起きしてみて、読書や勉強、旅行の計画などに時間を使ってみましょう。
それ以外には「ヤッター!」のポーズをとることも勧められています。朝起きたら、窓を開けてグーッと伸びをし、顔を上にあげ、両手を上に突き上げましょう。たったこれだけでもポジティブな気持ちになれます。
長期的な自己肯定感の高め方としては、「自己認知」「自己受容」「自己成長」という3つのステップに取り組むのがおすすめ。今の現実の自分を知る「自己認知」→今の自分を受け入れる「自己受容」→自己肯定感の木を育てる「自己成長」の3ステップにじっくり取り組んでいきましょう。自己認知には「ライフチャート」が、自己受容には「タイムライン」が、自己成長には「スリー・グッド・シングス」がおすすめされています。
本書を読み、一つひとつのトレーニングに取り組むことで、手ごたえが得られ、自ずと自己肯定感が上がっていくでしょう。短期的な自己肯定感の高め方と長期的な自己肯定感の高め方、2つのアプローチで着実に自己肯定感を上げたい人におすすめの本です。
敏感すぎるあなたが7日間で自己肯定感をあげる方法
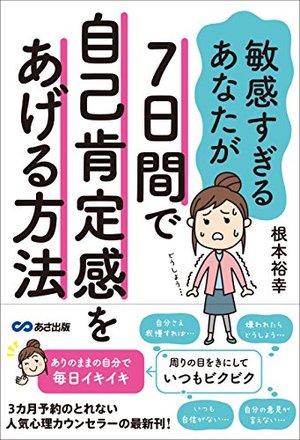
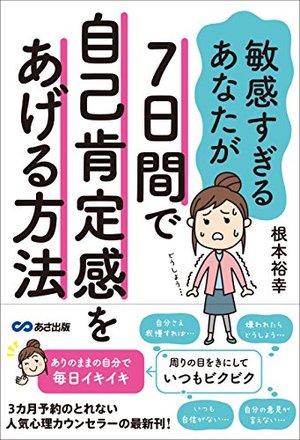
自己肯定感が低くて、毎日つらい思いをしている。短期間で確実に自己肯定感の高い自分に生まれ変わりたい――。そんな人には『敏感すぎるあなたが7日間で自己肯定感をあげる方法』をおすすめします。
本書では、心理カウンセラーの根本裕幸さんが、自己肯定感を高める7日間のプログラムをまとめています。その概要を紹介しましょう。
1日目:今の自分に意識を向ける
2日目:過去を見つめなおす
3日目:過去の家族関係を見つめなおす
4日目:自己肯定感を高める
5日目:自分のペースで人間関係を築く
6日目:敏感であることを強みにする
7日目:自分が本当にしたいことを実現する
本書を片手に、7日間だけ「自分の自己肯定感を高めること」に時間を投資してみませんか? その7日間はきっとあなたの人生において、ターニングポイントとなるはずです。
自己肯定感のコツ
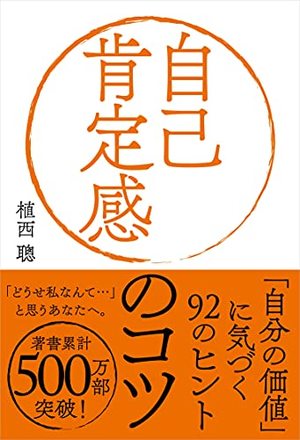
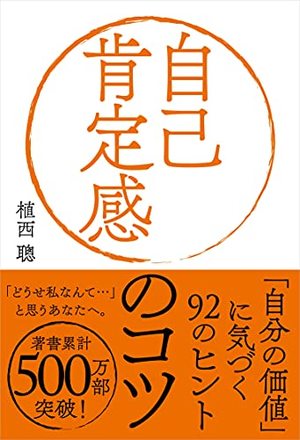
自己肯定感の高め方をたくさん知りたいあなたには、『自己肯定感のコツ』(植西聰著)がぴったり。「『元気』『陽気』を心がけて生きる」「もっと『気が利く人』になってみる」といった章立てで、自己肯定感を高める習慣がたっぷり紹介されています。今すぐ試せるものをいくつかピックアップしてみましょう。
まず「元気よく歩く」。うなだれながら歩くと気持ちが沈んでしまうもの。顔を上げて元気よく歩くだけでも、気分も自己肯定感も高まります。
「適度な運動をする」もおすすめ。運動をすると、脳の中でセロトニンという物質が分泌され、気持ちが前向きになるためです。心身の健康のために、軽い運動を習慣づけましょう。
最後に取り上げたいのは「小さな目標を着実に達成する」。大きな目標を細分化して「小さな目標」を設定し、着実に達成していく「スモール・ステップ」というメソッドは、自己肯定感アップに効果的だとされています。ごく小さな目標でもかまいません。一つひとつクリアすることで、自己肯定感を育みましょう。やがて大きな目標に挑戦できるようになるはずです。
脳の名医が教える すごい自己肯定感
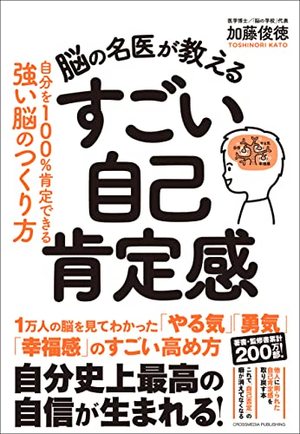
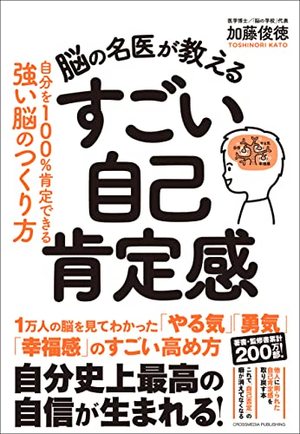
『脳の名医が教える すごい自己肯定感』は、脳内科医の加藤俊徳さんが、「脳の癖」に着目して自己肯定感にアプローチした一冊。
加藤さんによると、「自分はダメだ」「人よりも能力が低い」と感じる原因は脳の癖にあります。脳の仕組みとカラクリを理解し、考え方と行動を変えることで、自己肯定感アップにつながるのです。
ここでキーワードとなるのは、「自己否定」という言葉。自己否定に陥ると、脳の力が削がれてしまいます。その前提のもと、本書では、自己否定から抜け出して、自律的自己肯定感(自分の内的な基準に基づいた自己肯定感)を手に入れる方法が8つ提案されています。
そのうちの一つが、「自分基準」をつくるというもの。「自分が生きる上で何を一番大切な価値として考えているか」「自分の人生のテーマは何か」といった価値基準を明確に持ちましょう。
自分基準をつくるには、「人生の成功とは何かを決めること」と「自分の人生訓をつくること」が有効。この2つの取り組みにより、自分基準ができて、他人の基準に振り回されることがなくなります。
脳の性質を利用して自己肯定感アップをめざす本書。「自分は認知が歪んでいるのかも?」と思ったことのある人や、脳の癖を変えて生き方を変えたい人に、一読をおすすめします。
自己肯定感が高まる習慣力
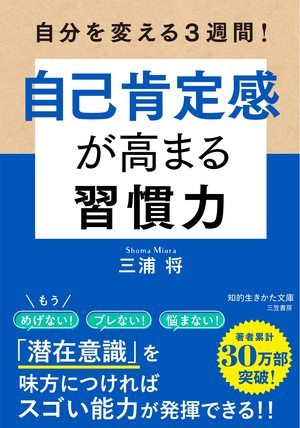
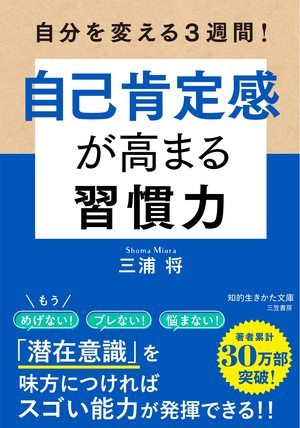
自己肯定感の低さの原因は「思い込み」にある――。そう断言するのは『自己肯定感が高まる習慣力』(三浦将著)です。
本書では、自己肯定感は「自分をどれだけ受け容れているか」の指標だとしたうえで、自己肯定感が高い人の例として、バカボンのパパが挙げられています。失敗しても「これでいいのだ」と言って、決して自分を否定しない。そんなバカボンのパパこそ、自己肯定感の高い人のお手本なのです。
著者の三浦さんは、自己肯定感が低くなる原因として「~でなければいけない」という思い込みが自己否定を引き起こすことを挙げています。しかもその思い込みは大抵、事実とは異なるもの。それでも私たちは、思い込みに振り回され続けてしまうのです。
本書では、思い込みを外す3ステップが紹介されています。
ステップ(1)自分の中の「思い込み」を見つける
ステップ(2)「やらないこと」を決める
ステップ(3)頑固な思い込みを解消する
ここでは本書から、ステップ(3)の「頑固な思い込みを解消する」習慣を2つ取り上げましょう。
1つ目の習慣は「例外を見つける」。頑固な思い込みであっても、例外を見つければ、思い込みを疑うことができるでしょう。
2つ目の習慣は「あだ名をつける」。たとえば「常に完璧でなければいけない」という思い込みを持っている人は、「常に完璧でなければいけない」と言い続けるキャラクターをつくり、“アイスマン”などとあだ名をつけてみましょう。そして「完璧にしなければいけない」という思い込みが顔を出したときに、「アイスマンが出てきた」と心の中で言ってみるのです。キャラクター化することで、思い込みと自分を切り離せる効果が期待できます。
自己肯定感の高め方が丁寧に示される本書を読み、実践すれば、自己肯定感の低い自分に別れを告げることができるでしょう。
小さなルーティン
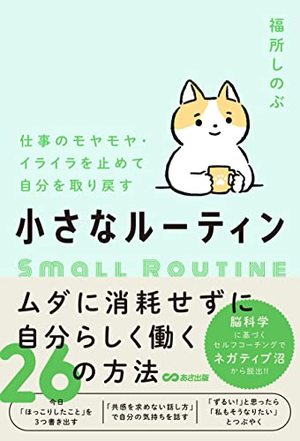
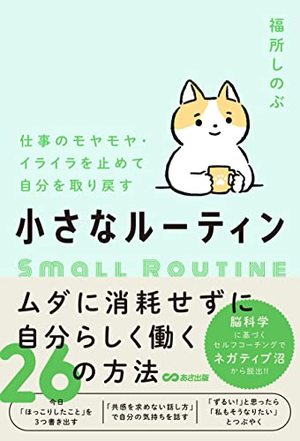
「もっと自分らしく働きたい」――。もしあなたがこの悩みを抱えているなら、『小さなルーティン』がヒントになるかもしれません。
本書の著者、福所しのぶさんによると、「自分らしく働けない」という悩みの原因は「ストレス思考」です。
福所さんによると、「ストレス思考」を手放すために必要なのは、「湧き上がった気持ちに気づき、認めること(自己肯定感)」と、「うまくいく方法を探すこと(メタ認知力)」。本書では、「自己肯定感」と「メタ認知力」をバランスよく育てるルーティンがまとめられています。
まず、ストレス思考の3つのタイプについて紹介しましょう。
1つ目は、自己肯定感もメタ認知力も低い「仕事でドキドキ」タイプ。
2つ目は、自己肯定感は高いがメタ認知力が低い「仕事でムカムカ」タイプ。
3つ目は、自己肯定感は低いがメタ認知力が高い「仕事でモヤモヤ」タイプ。
さて、あなたはどのタイプでしょう?
「自己肯定感」を高めるルーティンとしては、以下が効果的です。
・今日「ほっこりしたこと」を3つ書き出す
・ほめられたらすぐ「ありがとう」と返す
「メタ認知力」を高めるルーティンとしては、以下が効果的です。
・仕事以外の自分の役割に目を向ける
・モヤっとしたら4つに分けて書き出す
自己肯定感はもちろん、メタ認知力も高められる本書。仕事のドキドキ・ムカムカ・モヤモヤを手放し、自分らしく働きたい人におすすめの一冊です。
全米トップ校が教える自己肯定感の育て方
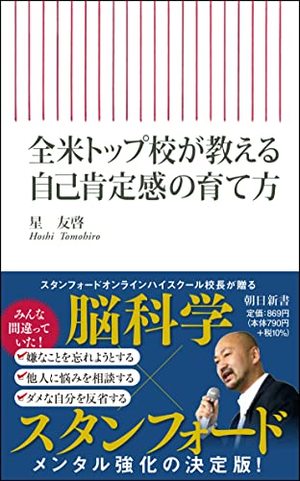
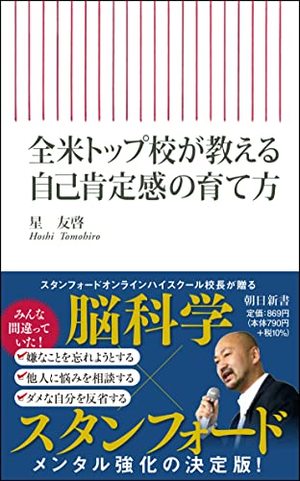
最新の心理学・脳科学的アプローチによる自己肯定感の高め方を知りたい人におすすめする本は『全米トップ校が教える自己肯定感の育て方』です。スタンフォード大学・オンラインハイスクール校長の星友啓さんが、自己肯定感の育て方を教えてくれます。
自己肯定感を引き出す方法としておすすめされているのは「TGTジャーナル」を習慣づけること。「TGT」とは『Three Good Things』の略で、その日にあった3つの良いことをジャーナル(日記)に書くことを言います。
TGTジャーナルをつける際のポイントは、以下の6つ。
(1)夜寝る前など、毎日決まったタイミングで書く
(2)その日に起きた良かったことを3つ探す
(3)3つの良かったことを「タイトル」「詳細」「その出来事についてどう感じたか」の要素を入れて書き留める
(4)3つの出来事が起きた理由を考える
(5)無理してたくさん書いたり、うまく書こうとしたりしない
(6)簡略化するなど、自分の続けやすい方法にカスタマイズする
本書の特徴は、自己肯定感の定義や高め方がとにかくシンプルにわかりやすくまとめられている点。自己肯定感を上げる食事法や手軽な瞑想法も紹介されているので、自己肯定感を高める習慣を取り入れたいなら、ぜひ読んでみてください。
「自己肯定感」育成入門


自分ではなく、我が子の自己肯定感を高めたい人にぴったりの本は『「自己肯定感」育成入門』です。これまで5万人以上が参加した“放課後NPOアフタースクール”代表理事の平岩国泰さんが、子どもの自己肯定感を育成する方法をまとめています。
特に注目したいのは、子どもが自己肯定感を育むためには、子どもがありのままでいられる「安全基地」の存在が重要であるということ。保護者には、「その子自身を見る」という姿勢で成長をほめる習慣をつけることが勧められています。
子どもの自己肯定感アップに関心のある人は、ぜひ手に取ってみてください。
「自己肯定感低めの人」のための本
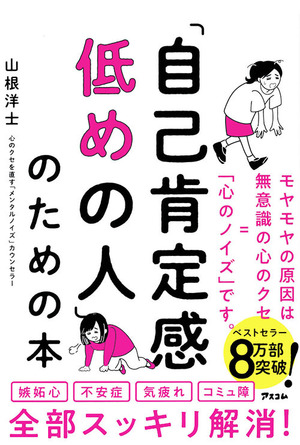
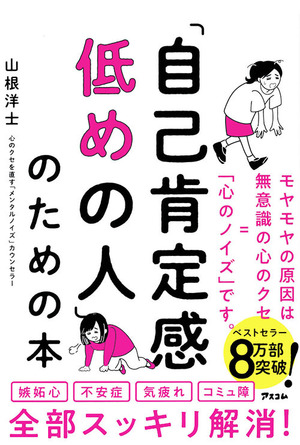
自分は自己肯定感が低めだという自覚がある。自己肯定感の高め方を知るというより、自己肯定感が低めでも悩まずに生きていく方法を知りたい――。そんな人におすすめする本は『「自己肯定感低めの人」のための本』です。
本書では、8000人以上の悩みを解決してきた心理カウンセラーの山根洋士さんが、自己肯定感を下げる原因は幼少期の経験から潜在意識に刻みつけられた「メンタルノイズ」であるとし、メンタルノイズに影響を受けないようにする方法を示してくれます。
本書によると、メンタルノイズとは、あなたがついやってしまう心のクセのこと。代表的なメンタルノイズは以下の14タイプに分類できます。自分のメンタルノイズがどのタイプか把握するだけでも、心が楽になるでしょう。
(1)ダメ出しノイズ=自分は重要でないほうがいい
(2)ありのままの自分封印ノイズ=自分のままでいないほうがいい
(3)思考停止ノイズ=自分は考えないほうがいい
(4)他人ファーストノイズ=欲しがらないほうがいい
(5)謙虚謙遜ノイズ=受け取らないほうがいい
(6)出ない杭ノイズ=達成しないほうがいい
(7)石の上にも三年ノイズ=がまんしたほうがいい
(8)他人がこわい裏切りノイズ=信用しないほうがいい
(9)ちゃんとしなきゃノイズ=子どもでないほうがいい
(10)幸福恐怖症ノイズ=幸せにならないほうがいい
(11)完璧主義ノイズ=完璧でないといけない
(12)タイムイズマネーノイズ=急がないといけない
(13)おもてなしノイズ=喜ばせないといけない
(14)ドMノイズ=努力しないといけない
本書では、メンタルノイズのタイプ別解説に加え、たった1分で取り組める、メンタルノイズに影響を受けないようにする方法(「ノイキャン」エクササイズ)が紹介されています。10種類のエクササイズが紹介されているので、気になったものから試してみませんか?
まとめ
「どんな本を選んでいいかわからない」「本を読む時間が取れない」「効率よくたくさんの本を読んで知識を得たい」という方は、1冊10分で読める本の要約サービス「flier(フライヤー)」を活用し、スキマ時間にインプットしてみてはいかがでしょうか。
話題の新刊から定番の名著まで、編集部が厳選したおすすめ本の要約を、ぜひチェックしてみてください。
▶スキルアップ・キャリアの要約一覧はこちら▶自己啓発・マインドの要約一覧はこちら
▶【無料体験】7日間の無料体験はこちら

