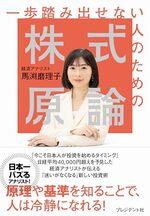論理的思考はひとつなのか
論理の文化的側面とは

論理的に考えることの重要性と必要性は広く共有されている。学術やビジネスから日常の判断に至るまで、論理的思考は世界共通で不変のもののように語られがちだ。しかし、そもそも論理的であるとはどのようなことなのだろうか。論理的に思考する方法は本当にひとつなのだろうか。
著者がこのような疑問を持ったのは、アメリカの大学に留学して、エッセイと呼ばれる小論文を提出した時だ。著者のエッセイは「評点不能」と突き返された。何度丁寧に書き直しても評価は変わらない。ところが、アメリカ式エッセイの構造を知って書き直すと、評価が三段跳びに良くなった。
論理的思考とは、実はグローバルに共通なものではなく、文化によって異なっている。同じ型を身に着けている人同士では円滑にコミュニケーションができる一方で、異なる型の文化圏の人を相手に自国の型で押し通そうとすれば、「論理的でない」と評価を下されることもある。先のエッセイの例は、論文の構造とそれに導かれた論理と思考法の日米の違いが衝突した結果である。
これは日本人が非論理的で、西洋的な書き方が論理的であるという意味ではない。「西洋」と一括りにされがちだが、アメリカとフランスの小論文の構造はまったく異なる。アメリカ式のエッセイは、自己の主張をわかりやすく効率的に論証して相手を説得するのが目的である。一方、フランス式の小論文の場合は、時間をかけてあらゆる可能性を吟味し矛盾を解決すること、さらにそれを公共の福祉という政治的判断に活かすことに重きが置かれる。論理的思考の型は、それぞれの社会がなにを重視し文化の中心に据えるのかと深くかかわり、目的によってエッセイの構造も変わってくるのだ。
文化の型と思考の型
こうした論理的思考の方法は無限にあるわけではなく、いくつかのタイプを「型」として提示することが可能だ。本書では「経済」「政治」「法技術」「社会」の4つの領域に分けて、それぞれに固有の論理と思考法を、「型(構造)」に注目して提示する。
経済のグローバル化と英語の覇権的地位の獲得に伴って、アメリカ式エッセイは世界標準の書き方と見なされている。これを学ぶことは、効率的なコミュニケーションを実現するうえでは有効であるが、それのみで押し通そうとすると、思わぬ落とし穴にはまることもある。







![[新書版]生きる意味](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ffd-flier-static-prod-endpoint-b6g9b5dkedfkeqcc.a03.azurefd.net%2Fsummary%2F4116_cover_150.jpg&w=3840&q=75)